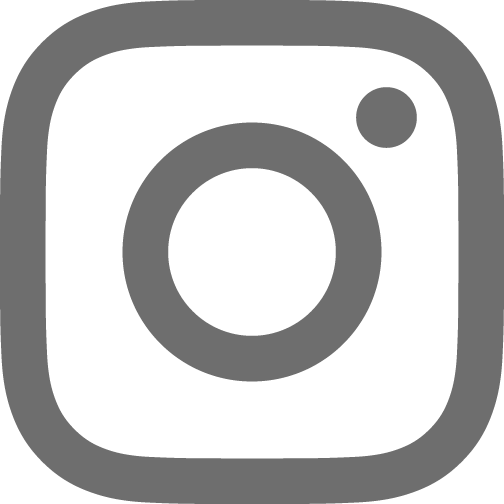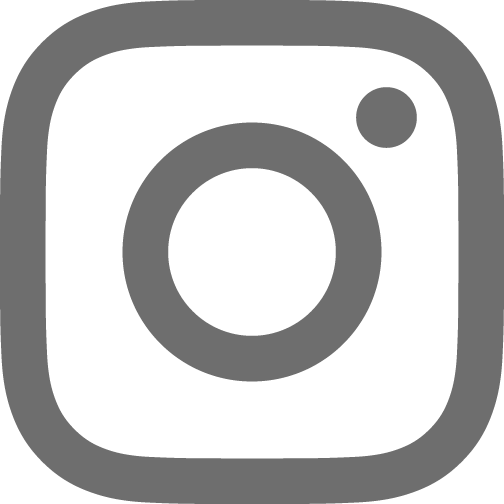「影の空間」のマネキン美
「影の空間」へ
通常、街で見かけるマネキンは、華やかな「光の空間」に存在している。しかし、服に眼を奪われるためか、マネキンそれ自体が興味の対象になることは少ない。一体マネキンはどのように作られ、いかなる運命を辿るものかと考えを巡らせる人は稀だ。普段、見ることのない「影の空間」に存在するマネキンの美しさにでも遭遇しなければ、興味を抱くことはなかろう。マネキンは商業活動の道具として流行の先端の服を身に付け、1世紀以上も人間と「共生」してきたが、その実態は依然として神秘のベールに包まれている。
マネキンと関わってきた人々は、人に夢や理想をもたらすために在るマネキンの「影の空間」における姿を、赤裸々に見せることを善しとしなかった。例えば、マネキンの原型が制作されるアトリエ。製品が作られる生産工場。夥しい数の裸体のマネキンが置かれている倉庫等は、「影の空間」に他ならない。マネキンの首や身体がバラバラにされて、半ば無造作に放置されている光景、平然と鋸で首や胴体を切断している様子に遭遇した人は、それが人工物と知りつつも、繊細な感性の持ち主であれば、「光の空間」におけるそれがまるで嘘のように異様な光景に映るだろう。しかし、こうした機会を得たクリエーターやジャーナリストの中には、「光の空間」では決して見せることのない、マネキンのただならぬ美しさに眼を奪われる人がいる。写真家・林雅之もその一人であるが、彼は誰よりも深く執物に「影の空間」に漂うマネキンの美に迫ったのである。
「生」と「死」
マネキン作家が創造力の限りを尽くして完成させた粘土原型は美しい。手の温もりとタッチが醸し出す粗野な美しさは魅力的だ。しかし、その「命」は儚い。石膏で型取りされるまでの僅かな時間、アトリエで見ることができる束の間の女神である。マネキンは型から量産される。そのための型取り作業は冷酷なまでに淡々と執り行なわれる。粘土原型は石膏で被われ、すっかり姿を隠してしまう。やがて石膏が硬化し離型すると、粘土が姿を現す。しかし、「命」の継承を担うのは石膏雌型であって、粘土のそれではない。石膏から取り外されたまだ造形の痕跡が残る役割を終えた粘土の塊は、無造作に粘土槽に投げ込まれ、次なる女神を生むその時までの間、暗く冷たい粘土槽の中で過ごすのである。
マネキンの美を目のあたりにする時、その美しさが生まれる過程で生じる粘土原型の消滅は、それがマネキンを生むための必然の結果であっても、丹精込めて創られた「ひとがた」であるがゆえに切ない。こうしてマネキンの「生」は、粘土原型のあっけない「死」によってもたらされる。その後、作家の手を離れ、仕上げ工程に移され、マスター型が完成する。その段階になると、作家の手の痕跡はほぼ失われている。そして、生産型が作られ量産工程に移行する。一つの型から多くの分身が生み出されるが、生まれた瞬間から歳をとらずに生き続け、美しい姿のまま死んで行く。
「影の空間」におけるマネキン美は、こうした存在の儚さと無関係ではない。
「体内」は暗い闇
すべて人間によって創造され、人の思いのままに存在し続け、人の思いが途絶えた時、役割を終えるのがマネキンである。しかし、数あるモノの中で、人間に近い姿かたちを表していることから、「生」と「死」に対するイメージは際立っている。マネキンが煌びやかな衣裳を身にまとい、該いばかりのスポットライトを浴びながら光輝いて見える時、厚さ3ミリの強化プラスチック製の「皮膚」で被われた「体内」は、人の思いが及ぶことのない暗くて空慮な闇の世界だ。その闇が「皮膚」の表面に浮き出てくる瞬間、即ち人の思いがマネキンに投影されなくなった時、それはマネキンにとって「死」の到来を意味している。「死」を宣告されたマネキンは、化粧されたまま傷つき汚れ、疲れ果て、無念の表情を浮かべ始める。そして、着脱可能な腕は外され、時には片脚のない哀れな姿をさらけ出し、マネキンの「墓場」に積み上げられる。思いを込め完成した瞬間と、「光の空間」を彩った幸福な時がまるで嘘のように、その末路は無残だ。そして、廃棄される瞬間を待つだけの日々を過ごす。その光景に遭遇した人は、そのものがひとがたであるがゆえに衝撃を受けるだろう。物言わぬマネキンは、人の感性や思いをそのまま映し出す鏡のような存在である。マネキンが輝いて見えるのも、哀れに見えるのも、すべて人間がもたらせた結果に過ぎない。顔が汚れていようが、付け睫毛が剥がれかけていようが、カツラが歪んでいようが、マネキン自体は不快感を露わにすることなく平然としている。そして、いかなる状態に置かれようと、マネキン自体は品格を問われることはない。問われるのは、そのような状態に無神経でいる人間の方なのだ。倉庫という「影の空間」に置かれたマネキンの表情は実に多彩である。
波乱万丈の「人生」
日本のマネキンの多くはレンタルであるために、商業空間とマネキン倉庫の間をトラックに乗せられて、常に行き来している。意志をすべて人に委ねているマネキンは、波乱万丈の「人生」を余儀なくされることが常だ。注文主の思いのままに、肌色、化粧、ヘアスタイルを変えながら流転の日々をおくる。いつも美しい化粧とヘアスタイルが与えられるわけではなく、時には全身を黒く塗装されたり、また白塗りされたり、真っ赤にされることも珍しくはない。化粧もなすがままだ。洗い流すことのないマネキンの肌色や化粧の上に、次々と新しい塗料や絵の具が積層される。売れっ子のマネキンは、幾重にも重なった過去から現在に至る肌色と、幾通りもの化粧された顔を内に秘めている。皮膚が何かの弾みで剥がれると、過去の肌色が現われるのだ。また、強化プラスチック製のマネキンは堅牢性に優れているとはいえ、転倒の状態いかんでかなりの重傷を負うことになる。大抵の傷は 補修により再生されるが、マネキンにとって 不幸な出来事に変わりはない。さらに悲劇的なことは、顔が必要ないとされた場合、首から切断されヘッドレスマネキンにされることだ。首のない人間が服を着て立っていること自体、絶対にありえないことだが、これまで気味が悪いので取り下げたいとの話は聞いたことがない。さらに、特殊な例だが、少女のマネキンを中性的な少年のマネキンに作り変えるため、胸を削りとってしまったことがあった。その他、脚や腕、顔半分の切断などの人体改造や各種整形手術は、日常茶飯事である。こうして見ると、同じ型から作られた同じかたちのマネキンでも、その「人生」は波乱万丈なのだ。
林雅之の眼差しと感性
それぞれの「人生」を背負った夥しい数のマネキンが、所狭しと林立するマネキン倉庫の空間は異様である。悲喜こもごもの「人生」の途上にあるマネキンたちが眼を見開いたまま、両腕を外され肩を寄せ合い立ち並んでいる。傷つき汚れたマネキン。美しく化粧された顔のままで次の出番を待つマネキン。嬉々としている売れっ子のマネキン。薄暗い倉庫の片隅で一点を見つめたまま、じっと出番を待ち続けるマネキン。まだ一度も化粧されたことも服を着せられたこともなく、裸体のままその時を待つマネキン……。この「影の空間」に一歩足を踏み入れ、無数のマネキンたちにとり囲まれた時、恐怖感にも似たただならぬ気配に圧倒されるはずだ。ところが、気持ちを鎮めて倉庫のマネキンたちを見つめてみると、「光の空間」では決して見せることのない美しさに気付く。それは、偶然に生まれる美しさであり、人間の想像力が描き、感じとる美しさに他ならない。例えば、薄暗い蛍光灯の光の中に、ほんやりと浮かび上がる顔、窓から差し込む夕陽を受けて、紅色に染まる身体などは、人工的には再現不可能の美しさなのだ。
林雅之は、マネキン会社である七彩の倉庫に無造作に立ち並ぶマネキンに心惹かれ、たびたび足を運び続け、「影の空間」におけるマネキンの美に迫ってきた写真家である。林によれば、カメラを手に倉庫に入り、夥しい数のマネキンに次々と視線を投げ掛けながら歩くと、その中に「私を見て!」と微かな反応を返してくるマネキンに出会うそうだ。林は撮影の際に、 人工照明を使用したり、マネキンの位置を故意に変えることはしない。ありのままの状況から、自分に訴えかけてくるマネキンを求めて、林立するマネキンの中をひたすら歩き回る。静寂さが支配する倉庫のどこからか、シャッター音が聞こえる。それは林がマネキンに反応した瞬間だ。マネキンにしてみれば、 無防備な姿を撮影されることはさぞかし屈辱だろう。しかし、林がそうした姿を興味本位に記録する写真家でないことをマネキンは知っている。マネキンに向けられる林の眼差しは、一点の濁りもない純枠さと繊細さに充ちており、 撮影現場には時間が停止してしまったかのような緊張感が漂う。それゆえに写し出されたマネキンの表情は、「光の空間」では決して見せることのない、より深い美と穏やかさを湛えている。林が撮影した数ある写真の中で、長年カツラ製作用に使われている上半身マネキンを記録した作品は衝撃的だ。鬼気迫るその姿態に向けられた視点は限りなく優しい。 再び、美しい服を身にまとうことも、スポットライトを浴びることもない汚れきったそのマネキンは、 新たな美の創造のために自らを犠牲にしているのだ。その汚れは、人に愛され続けた証明であり、見放された結果ではない。人の愛に包まれたマネキンは、それが どのような姿になっても美しい存在であり続けると思う。その意味で 林雅之は、究極のマネキン美に迫った写真家と言えよう。
藤井秀雪 ふじいひでゆき 京都造形芸術大学教授空間演出デザイン研究センター主任研究員のデザイン研究」等に取組む。日本の歴史あるマネキン会社七彩に41年間動務。2003年4月定年退職。在職中は、広報宣伝をつとめながら、マネキンの歴史研究に取組む。